●歌は、「秋の野に咲きたる花を指折りかき数ふれば七種の花」である。

●歌をみていこう。
◆秋野尓 咲有花乎 指折 可伎數者 七種花 其一
(山上憶良 巻八 一五三七)
≪書き下し≫秋の野に咲きたる花を指(および)折りかき数(かぞ)ふれば七種(ななくさ)の花 その一
(訳)秋の野に咲いている花、その花を、いいか、こうやって指(および)を折って数えてみると、七種の花、そら、七種の花があるんだぞ。(伊藤 博著「萬葉集 二」角川ソフィア文庫より)
一五三七歌は、「其一」となっており、一五三八歌は「其二」とある。伊藤 博氏は、脚注で、「組で一つの内容をなす謡い物であることを示す注。子供向けに指折り数えた歌らしい。」と書かれている。
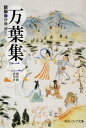 |
新版 万葉集 二 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) [ 伊藤 博 ] 価格:1,100円 |
![]()
一五三八歌もみてみよう。
◆芽之花 乎花葛花 瞿麦之花 姫部志 又藤袴 朝▼之花 其二
(山上憶良 巻八 一五三八)
▼は「白」の下に「八」と書く。「朝+『白』の下に『八』」=「朝顔」
≪書き下し≫萩の花 尾花(をばな) 葛花(くずはな) なでしこの花 をみなへし また藤袴(ふぢはかま) 朝顔の花
(訳)一つ萩の花、二つ尾花、三つに葛の花、四つになでしこの花、うんさよう、五つにおみなえし。ほら、それにまだあるぞ、六つ藤袴、七つ朝顔の花。うんさよう、これが秋の七種の花なのさ。(同上)
一五三七歌については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その61改)」で、一五三八歌については、「同(その62改)」で紹介している。
➡


東邦大学HP「薬草園の世界」の「秋の七草と薬効」コンテンツに、「秋の七草はハギ、ススキ、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウの七つの植物です。この七草の顔ぶれは、万葉集(巻八)で山上憶良(やまのうえのおくら)が詠んだ歌に由来しています。・・・一口に秋の七草と言っても、それぞれに生育に適した場所や開花期も少しずつずれていて、自然の中でこの7種の植物をまとめて楽しむのはなかなか難しいことのようです。春の七草は食用、秋の七草は観賞用などと言われますが、秋の七草に挙げられる植物の中には、薬草として用いられてきたものが6種もあります。今回は花と共にその薬草としての一面もご紹介します。」と書かれ、「東邦大学薬用植物園に咲いた秋の七草」が紹介されている。
順にみてみよう。(写真は、「東邦大学薬用植物園に咲いた秋の七草」より引用させていただきました。)
■ハギ■
【薬用部分】根
【薬効と薬理】民間:婦人のめまい、のぼせなどにどに効果があると言われます。

■ススキ■
残念ながら、ススキには薬効はないようです。

■クズ■
【薬用部分】根 (生薬名:葛根<カッコン>)
【薬効と薬理】葛根は発汗、解熱、鎮痙薬として、熱性病、感冒、首・背・肩こりなどに用いられます。 花(葛花<カッカ>)も眩暈や悪寒に用いられます。

■ナデシコ■
【薬用部分】全草(生薬名:<クバク>) 種子(生薬名:<クバクシ>)
【薬効と薬理】薬理効果は未詳。 全草・種子ともに消炎、利尿、通経薬として水腫、小便不利、淋疾、月経不順などに用いられます。流産の危険性があるので妊婦は決して用いてはいけません。

■オミナエシ■
【薬用部分】根(生薬名:敗醤根<ハイショウコン>) 全草(生薬名:敗醤草<ハイショウソウ>)
【薬効と薬理】根と全草に鎮静、抗菌、消炎、浄血などの作用があり、腸炎などによる腹痛、下痢、肝炎、腫痛、婦人病などに用いられています。サポニンによる溶血作用があるため、連用は避けた方がよく、強度の貧血の場合には用いてはなりません。

■フジバカマ■
【薬用部分】根(生薬名:敗醤根<ハイショウコン>) 全草(生薬名:敗醤草<ハイショウソウ>)
【薬効と薬理】根と全草に鎮静、抗菌、消炎、浄血などの作用があり、腸炎などによる腹痛、下痢、肝炎、腫痛、婦人病などに用いられています。サポニンによる溶血作用があるため、連用は避けた方がよく、強度の貧血の場合には用いてはなりません。

■キキョウ■<あさがほ
【薬用部分】根(生薬名:桔梗根<キキョウコン>)
【薬効と薬理】桔梗の煎剤はサポニンの局所刺激による去痰作用があります。
鎮静、鎮痛、解毒作用のほか、抗炎症、鎮咳、血圧降下作用などが認められます。
去痰、鎮咳薬として、痰、気管支炎、咽頭痛などに用いられます。

■■土佐豊永万葉植物園→山口県周南市若草町周南緑地公園西緑地万葉の森■■
土佐豊永万葉植物園で102基の万葉歌碑と対面し、次の目的地山口県周南市若草町周南緑地公園西緑地万葉の森を目指す。ホテルは下松市内である。
瀬戸大橋を渡る前に昼食を取るべく大歩危・小歩危の祖谷蕎麦もみじ亭に立ち寄る。そこまでは良かったが、ナビは国道319号線から高知自動車道軽油瀬戸大橋ルートを指示している。土地勘がないのでナビの言うとおり走るが、国道とは言うが、くねくねの狭い左側は山、右側は谷の山道である。すれちがった車わずかに3台。ほとんど利用されていない道なのだろう。不安に駆られながらも進まざるをえない。岐阜の時もそうであったが、辺鄙な山道を指示するナビ。過酷な試練にあわせるナビである。
事前にはグーグルのストリートビューで周南緑地万葉公園を確認していたのであるが、西緑地、中央緑地、東緑地、横浜緑地、遠石緑地の5つの緑地を総称して周南緑地とよばれているので、ナビだと絞り切れない。
ようやく周南緑地公園西緑地に到着したのは16時30分ごろであった。しかも万葉公園の歌碑と反対の入口のようである。歩いていくにしても往復を考えると結構時間を食いそうであるので車で挑戦するも土地勘の無さ。目的地にたどりつけない。迷いこんだのが「万葉プラザ・遠石市民センター」であった。ここで万葉歌碑の場所を尋ねる。職員の方が、これから帰るところなので案内しますので車の後からついてくるようにと、おっしゃってくださった。有り難いことであった。
ブログ紙面を借りて改めて御礼申し上げます。
万葉歌碑巡りでは、幾たびとなくご親切な方に巡り合える。まさに奇跡であり、有り難く心強いかぎりである。
(参考文献)
★「萬葉集」 鶴 久・森山 隆 編 (桜楓社)
★「weblio古語辞典 学研全訳古語辞典」
★「薬草園の世界」 (東邦大学HP)