●歌は、「ますらをは名をし立つべし後の世に聞き継ぐ人も語り継ぐがね(四一六五歌)」と
「鶉鳴く古りにし里ゆ思へども何ぞも妹に逢ふよしもなき(七七五歌)」である。

●歌をみていこう。
■四一六五歌■
◆大夫者 名乎之立倍之 後代尓 聞継人毛 可多里都具我祢
(大伴家持 巻十九 四一六五)
≪書き下し≫ますらをは名をし立つべし後の世に聞き継ぐ人も語り継ぐがね
(訳)ますらおたる者は、名を立てなければならない。のちの世に聞き継ぐ人も、ずっと語り伝えてくれるように。(伊藤 博 著 「万葉集 四」 角川ソフィア文庫より)
 |
新版 万葉集 四 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) [ 伊藤 博 ] 価格:1,068円 |
![]()
四一五九歌から四一六五歌までの歌群の総題は、「季春三月九日擬出擧之政行於舊江村道上属目物花之詠并興中所作之歌」<季春三月の九日に、出擧(すいこ)の政(まつりごと)に擬(あた)りて、古江の村(ふるえのむら)に行く道の上にして、物花(ぶつくわ)を属目(しょくもく)する詠(うた)、并(あは)せて興(きよう)の中(うち)に作る歌>である。
さらに、四一六四、四一六五歌の題詞は、「慕振勇士之名歌一首 并短歌」<勇士の名を振(ふる)はむことを慕(ねが)ふ歌一首 幷(あは)せて短歌」である。
左注は、「右二首追和山上憶良臣作歌」<右の二首は、追和山上憶良臣(やまのうえのおくらのおみ)が作る歌に追(お)ひて和(こた)ふ>である。
四一五九から四一六五歌については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その867)」で紹介している。
➡
山上憶良の歌は、九七八歌である。こちらもみてみよう。
◆士也母 空應有 萬代尓 語継可 名者不立之而
(山上憶良 巻六 九七八)
≪書き下し≫士(をのこ)やも空(むな)しくあるべき万代(よろづよ)に語り継(つ)ぐべき名は立てずして
(訳)男子たるもの、無為に世を過ごしてよいものか。万代までも語り継ぐにたる名というものを立てもせずに。(伊藤 博 著 「万葉集 二」 角川ソフィア文庫より)
(注)「名をたてる」ことを男子たる者の本懐とする、中国の「士大夫思想」に基づく考え。
左注は、「右の一首は、山上憶良の臣が沈痾(ちんあ)の時に、藤原朝臣八束(ふじはらのおみやつか)、河辺朝臣東人(かはへのあそみあづまひと)を使はして疾(や)める状(さま)を問はしむ。ここに、憶良臣、報(こた)ふる語(ことば)已(を)畢(は)る。しまらくありて、涕(なみた)を拭(のご)ひ悲嘆(かな)しびて、この歌を口吟(うた)ふ。」である。
(注)ちんあ【沈痾】:久しくなおらない重い病。(広辞苑無料検索)
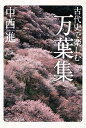 |
古代史で楽しむ万葉集 (角川ソフィア文庫) [ 中西 進 ] 価格:775円 |
![]()
中西 進氏は、その著「古代史で楽しむ万葉集」(角川ソフィア文庫)の中で、「もはや死を覚悟した憶良の『須ありて』という、しばらくの沈黙は、その生涯への回想の無限の感慨を物語っていよう。その物思いの後に口吟した一首であれば、これは空しく死んでいく士われへの、悔恨の一首だったのであろう。」と書かれている。
また同氏は、辰巳正明 著 「山上憶良」(笠間書院)の【付録エッセイ】「『士(をのこ)』として歩んだ生涯―みずからの死」のなかで、「『べし』ということばが二度も使われています。『かくあらねばならない』という思いがひじょうに強かったことは一目瞭然です。・・・しかも、『士やも空しくあるべき』とうたいだしています。―『士』が空しくあってもいいのか。いや、いけない。生涯最後の結論が反語であるのも、いかにも『相克(そうこく)と迷妄(めいもう)』を繰り返した憶良にふさわしいように思えます。」と書かれている。
この一首を辞世として、憶良は間もなく他界したのである。
憶良の九七八歌を理解してはじめて、家持の四一六四、四一六五歌の真髄に迫ることができるのである。
 |
価格:1,320円 |
![]()
■七七五歌■
題詞は、「大伴宿祢家持贈紀女郎歌一首」<大伴宿禰家持、紀女郎(きのいらつめ)に贈る歌一首>である。
◆鶉鳴 故郷従 念友 何如裳妹尓 相縁毛無寸
(大伴家持 巻四 七七五)
≪書き下し≫鶉(うづら)鳴く古(ふ)りにし里ゆ思へども何(なみ)ぞも妹(いも)に逢ふよしもなき
(訳)鶉の鳴く古びた里にいた頃からずっと思い続けてきたのに、どうしてあなたにお逢いするきっかけもないのでしょう。(「万葉集 一」 伊藤 博 著 角川ソフィア文庫より)
(注)うずらなく【鶉鳴く】:[枕]ウズラは草深い古びた所で鳴くところから「古(ふ)る」にかかる。(weblio辞書 デジタル大辞泉)
(注)にし 分類連語:…てしまった。(学研)
(注)よし【由】名詞:①理由。いわれ。わけ。②口実。言い訳。③手段。方法。手だて。④事情。いきさつ。⑤趣旨。⑥縁。ゆかり。⑦情趣。風情。⑧そぶり。ふり。(学研)ここでは③の意
 |
新版 万葉集 一 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) [ 伊藤 博 ] 価格:1,056円 |
![]()
この歌については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その945)」で紹介している。
➡
■■■伏見稲荷大社の境内社「伏見神宝神社」ならびに井手の玉川「歌碑の道」■■■
3月13日インスタなどで掲載されていた伏見稲荷大社の境内社「伏見神宝神社」の大伴家持の歌碑と井手の玉川「歌碑の道」の橘諸兄の歌碑を巡って来た。
伏見稲荷大社の駐車場に車を停める。

伏見稲荷大社参道には、修学旅行生や外国人が結構多く、コロナ問題もようやく落ち着きを見せたことを裏付けるかのような賑わいであった。


境内案内図を参考に千本鳥居を上って行く。
「伏見神宝神社」は、伏見稲荷大社の千本鳥居の途中のわき道から150mほどのところにある。これが結構きつい上り道である。ここでも万葉歌碑巡りは体力挑戦の旅でもあると、思い知らされる。
ほとんどの人は千本稲荷を上って行くので、伏見神宝神社へは行く人は、数えるほどであった。
もたもた歩いているので、150mほどのあいだで2グループ数人に追い越される。まもなく彼らは下りて来る。
ようやく神社に到着。静まり返ったこじんまりした境内、異空間である。



(参考文献)
★「萬葉集」 鶴 久・森山 隆 編 (桜楓社)
★「weblio古語辞典 学研全訳古語辞典」
★「広辞苑無料検索」