福岡県は、犬養 孝著「万葉の旅 上・中・下」平凡社ライブラリーの「万葉歌所出地名分布の表」では、全国で6番目になっている。
ちなみに順位をみてみると、奈良県(897)、大阪府(218)、滋賀県(145)、兵庫県(142)、富山県(140)、福岡県(129)である。(歌、題詞、左注の地名数の計)
福岡県の万葉歌碑については、福岡県1⃣京都郡みやこ町、2⃣北九州市<1>、3⃣北九州市<2>・宗像市・福岡市、4⃣太宰府市(1)、5⃣太宰府市(2)、6⃣太宰府市(3)の順で紹介していきます。
福岡県京都郡(みやこぐん)みやこ町の豊前国府跡公園の万葉歌の森には、万葉歌碑が10基立てられている。主な歌碑を紹介していこう。
1⃣京都郡みやこ町
■豊前国府跡公園万葉歌の森万葉歌碑(巻六 九五九)■

●歌をみていこう。
標題は、「冬十一月大宰官人等奉拜香椎廟訖退歸之時馬駐于香椎浦各述作懐歌」<冬の十一月に、大宰(だざい)の官人等(たち)、香椎(かしい)の廟(みや)を拝(をろが)みまつること訖(をは)りて、退(まか)り帰る時に、馬を香椎の浦に駐(とど)めて、おのもおのも懐(おもひ)を述べて作る歌>である。
題詞は、「豊前守宇努首男人歌一首」<豊前守(とよのみちのくちのかみ)宇努首男人(うののおびとをひと)が歌一首>である。
(注)宇努首男人:百済系渡来人の子孫。養老四年(720年)以来豊前守。
◆徃還 常尓我見之 香椎滷 従明日後尓波 見縁母奈思
(宇努首男人 巻六 九五九)
≪書き下し≫行く帰り常に我(わ)が見し香椎潟(かしひかた)明日(あす)ゆ後(のち)には見むよしもなし
(訳)大宰府への行きにも帰りにも、いつも見馴れた香椎の潟、私にとってもそんなに懐かしい香椎潟でありますが、明日からのちは見るすべもありません。(「万葉集 二」 伊藤 博 著 角川ソフィア文庫より)
(注)明日ゆ後には:遷任することが決まっていたのであろう。
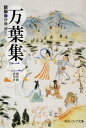 |
新版 万葉集 二 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) [ 伊藤 博 ] 価格:1,100円 |
![]()
この歌ならびに歌碑については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その873)」で紹介している。
➡


■豊前国府跡公園万葉歌の森万葉歌碑(巻十六 三八七六)■

●歌をみていこう。
題詞は、「豊前國白水郎歌一首」<豊前(とよのみちのくち)の国の白水郎(あま)の歌一首>である。
(注)はくすいろう【白水郎】:《「白水」は中国の地名。水にもぐることのじょうずな者がいたというところから》漁師。海人(あま)。(コトバンク 小学館デジタル大辞泉)
◆豊國 企玖乃池奈流 菱之宇礼乎 採跡也妹之 御袖所沾計武
(作者未詳 巻十六 三八七六)
≪書き下し≫豊国(とよくに)の企救(きく)の池なる菱(ひし)の末(うれ)を摘むとや妹がみ袖濡れけむ
(訳)豊国の企救(きく)の池にある菱の実、その実を摘もうとでもして、あの女(ひと)のお袖があんなに濡れたのであろうか。(伊藤 博 著 「万葉集 三」 角川ソフィア文庫より)
(注)企救(きく):北九州市周防灘沿岸の旧都名。フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の小倉市の歴史の項に「律令制下では豊前国企救郡(きくぐん)の一地域となる。」とある。
(注)袖濡れえむ:自分への恋の涙で濡れたと思いなしての表現。(伊藤脚注)
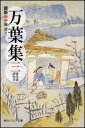 |
新版 万葉集 三 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) [ 伊藤 博 ] 価格:1,068円 |
![]()
この歌ならびに歌碑については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その874)」で紹介している。
➡
■豊前国府跡公園万葉歌の森(4)万葉歌碑(巻三 三一一)■

●歌をみていこう。
題詞は、「▼作村主益人従豊前國上京時作歌一首」<▼作村主益人(くらつくりのすぐりますひと)、豊前(とよのみちのくち)の国より京へ上(のぼ)る時に作る歌一首>である
(注)▼作村主益人:伝未詳
※ ▼は「木(へん)+安」で「くら」である。
◆梓弓 引豊國之 鏡山 不見久有者 戀敷牟鴨
(▼作村主益人 巻三 三一一)
≪書き下し≫梓弓(あづさゆみ)引き豊国(とよくに)の鏡山(かがみやま)見ず久(ひさ)ならば恋(こひ)しけむかも
(訳)梓弓を引っ張って響(とよ)もすという豊の国、住み馴れた豊国の鏡山、この山を久しく見ないようになったら、恋しく思われてならないだろうな。(「万葉集 一」 伊藤 博 著 角川ソフィア文庫より)
(注)あづさゆみ【梓弓】分類枕詞:①弓を引き、矢を射るときの動作・状態から「ひく」「はる」「い」「いる」にかかる。②射ると音が出るところから「音」にかかる。③弓の部分の名から「すゑ」「つる」にかかる。(学研)
(注)「梓弓引き」は、序。「豊國」を起こす。引っぱって響(とよ)もすの意。(伊藤脚注)
(注)鏡山:福岡県田川郡香春(かわら)の町の山
この歌ならびに歌碑については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その872)」で紹介している。
➡
■豊前国府跡公園万葉歌の森万葉歌碑(巻九 一七六七)■

●歌をみていこう。
◆豊國乃 加波流波吾宅 紐兒尓 伊都我里座者 革流波吾家
(抜気大首 巻九 一七六七)
≪書き下し≫豊国(とよくに)の香春(かはる)は我家(わぎへ)紐児(ひものこ)にいつがり居(を)れば香春は我家
(訳)豊の国の香春は我が家だ。かわいい紐児にいつもくっついていられるのだもの。香春は我が家だ。(「万葉集 二」 伊藤 博 著 角川ソフィア文庫より)
(注)香春:福岡県田川郡香春(かわら)町。(伊藤脚注)
(注)紐児:遊行女婦の名か。(伊藤脚注)
(注)いつがる【い繫る】自動詞:つながる。自然につながり合う。 ※上代語。「い」は接頭語。(学研)
旅先の地を「我が家」と詠うことで、溢れんばかりの愛情を込め、「香春は我が家」と二度繰り返してその喜びを歌い上げている。
この歌ならびに歌碑については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その878)」で紹介している。
➡
■豊前国府跡公園万葉歌の森万葉歌碑(巻三 三二八)■

●歌をみてみよう。
◆青丹吉 寧樂乃京師者 咲花乃 薫如 今盛有
(小野老 巻三 三二八)
≪書き下し≫あをによし奈良の都は咲く花のにほふがごとく今盛りなり
(訳)あをによし奈良、この奈良の都は、咲き誇る花の色香が匂い映えるように、今こそまっ盛りだ。(「万葉集 一」 伊藤 博 著 角川ソフィア文庫より)
 |
新版 万葉集 一 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) [ 伊藤 博 ] 価格:1,056円 |
![]()
この歌ならびに歌碑については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その870)」で紹介している。
➡

以上紹介した以外の豊前国府跡公園万葉歌の森万葉歌碑5基は、次のとおりである。


5月16日、奈良県宇陀郡曽爾村「隼別神社(はやぶさわけじんじゃ)」の万葉歌碑を写しに行ってきました。
「隼別神社」は、平成二年に奈良市の方が若宮神社(祭神は隼別皇子)の近くのこの地を訪れた際、古い石組みを見て隼別皇子を祀った跡と確信し社を建てたという。
隼別皇子(はやぶさわけのみこ:仁徳天皇の弟)は、仁徳天皇の許しを得ず、雌鳥皇女(めどりにひめみこ)と結ばれる。このことを知り、さらに皇子に謀叛(むほん)の疑いがあるとして伊勢神宮に逃げようとした二人を曽爾で捕らえ殺したという悲劇が日本書紀や古事記に記されている。
「隼別神社」には、二人の歌碑と共に26基の歌碑が立てられている。万葉集に因んだ歌碑は、額田王(巻一 一八歌)、大伯皇女(巻二 一六五歌)、柿本人麻呂(巻三 二六六歌)の3基である。
詳細は、後日改めて紹介いたします。


(参考文献)
★「萬葉集」 鶴 久・森山 隆 編 (桜楓社)
★「万葉の旅 上・中・下」 犬養 孝著 (平凡社ライブラリー)
★「weblio古語辞典 学研全訳古語辞典」
★「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」