■島根県益田市 県立万葉公園石見の広場万葉歌碑(巻三 三七一)■

●歌をみていこう。
題詞は、「出雲守門部王思京歌一首 後賜大原真人氏也」<出雲守(いづものかみ)門部王(かどへのおほきみ)、京を思(しの)ふ歌一首 後に大原真人の氏を賜はる>である。
◆飫海乃 河原之乳鳥 汝鳴者 吾佐保河乃 所念國
(門部王 巻三 三七一)
≪書き下し≫意宇(おう)の海の川原(かはら)の千鳥汝(な)が鳴けば我(わ)が佐保川の思ほゆらくに)
(訳)意宇(おう)の海まで続く川原の千鳥よ、お前が鳴くと、わが故郷の佐保川がしきりに思いだされる。(同上)
(注)おう【意宇・淤宇・飫宇】:島根県北東部にあった郡。ここに国府が置かれた。
(注)意宇(おう)の海:現在の島根県の中海。(伊藤脚注)
 |
新版 万葉集 一 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) [ 伊藤 博 ] 価格:1,056円 |
![]()
この歌ならびに歌碑については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その1261)」で紹介している。
➡

■島根県益田市 県立万葉公園石見の広場万葉歌碑(巻三 三五五)■

●歌をみていこう。
題詞は、「生石村主真人歌一首」<生石村主真人(おひしのすぐりまひと)が歌一首>である。
◆大汝 小彦名乃 将座 志都乃石室者 幾代将經
(生石村主真人 巻三 三五五)
≪書き下し≫大汝(おおなむち)少彦名(すくなびこな)のいましけむ志都(しつ)の石室(いはや)は幾代(いくよ)経(へ)ぬらむ
(訳)大国主命(おおくにぬしのみこと)や少彦名命が住んでおいでになったという志都の岩屋は、いったいどのくらいの年代を経ているのであろうか。(「万葉集 一」 伊藤 博 著 角川ソフィア文庫より)
(注)おおあなむちのみこと【大己貴命】:「日本書紀」が設定した国の神の首魁(しゅかい)。「古事記」では大国主神(おおくにぬしのかみ)の一名とされる。「出雲風土記」には国土創造神として見え、また「播磨風土記」、伊予・尾張・伊豆・土佐各国風土記の逸文、また「万葉集」などに散見する。後世、「大国」が「大黒」に通じるところから、俗に、大黒天(だいこくてん)の異称ともされた。大穴牟遅神(おおあなむぢのかみ)。大汝神(おほなむぢのかみ)。大穴持命(おほあなもちのみこと)。(コトバンク 精選版 日本国語大辞典)
(注)少彦名命 すくなひこなのみこと:記・紀にみえる神。「日本書紀」では高皇産霊尊(たかみむすびのみこと)の子、「古事記」では神産巣日神(かみむすびのかみ)の子。常世(とこよ)の国からおとずれるちいさな神。大国主神(おおくにぬしのかみ)と協力して国作りをしたという。「風土記」や「万葉集」にもみえる。穀霊,酒造りの神,医薬の神,温泉の神として信仰された。「古事記」では少名毘古那神(すくなびこなのかみ)。(コトバンク 講談社デジタル版 日本人名大辞典+Plus)
(注)志都の石室:島根県大田市静間町の海岸の岩窟かという。(伊藤脚注)
(注の注)静之窟(しずのいわや):「静間川河口の西、静間町魚津海岸にある洞窟です。波浪の浸食作用によってできた大きな海食洞で、奥行45m、高さ13m、海岸に面した二つの入口をもっています。『万葉集』の巻二に『大なむち、少彦名のいましけむ、志都(しず)の岩室(いわや)は幾代経ぬらむ』(生石村主真人:おおしのすぐりまひと)と歌われ、大巳貴命(おおなむちのみこと)、少彦名命(すくなひこなのみこと)2神が、国土経営の際に仮宮とされた志都の石室はこの洞窟といわれています。洞窟の奥には、大正4年(1915)に建てられた万葉歌碑があります。現在崩落により、立入禁止となっています。」(しまね観光ナビHP)
この歌ならびに歌碑については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その1262)」で紹介している。
➡
上述(注の注)の静之窟(しずのいわや)の歌碑(静之窟説明案内板)については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その1342)」で紹介している。
➡

■島根県益田市 県立万葉公園石見の広場万葉歌碑(巻七 一二四九)■

20211012撮影
●歌をみてみよう。
◆君為 浮沼池 菱採 我染袖 沾在哉
(柿本人麻呂歌集 巻七 一二四九)
≪書き下し≫君がため浮沼(うきぬ)の池の菱(ひし)摘むと我(わ)が染(そ)めし袖濡れにけるか
(訳)あの方に差し上げるために、浮沼の池の菱の実を摘もうとして、私が染めて作った着物の袖がすっかり濡れてしまいました。(伊藤 博 著 「万葉集 二」 角川ソフィア文庫より)
(注)浮沼(うきぬ)の池;所在未詳。(伊藤脚注)
うきぬ【浮沼】について、「コトバンク 精選版 日本国語大辞典」に次のように書かれている。
「〘名〙 泥深い沼。蓴(ぬなわ)や菱などの水草が繁茂するような泥沼。多く『うきぬのいけ』として和歌に用いる。うきぬま。
[補注]:『浮沼の池』を島根県大田市三瓶山付近の地名として歌枕とする説がある(大日本地名辞書)。」
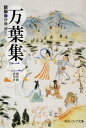 |
新版 万葉集 二 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) [ 伊藤 博 ] 価格:1,100円 |
![]()
■島根県益田市 県立万葉公園石見の広場万葉歌碑(巻三 一二五〇)■

20211012撮影
●歌をみていこう。
◆妹為 菅實採 行吾 山路惑 此日暮
(柿本人麻呂歌集 巻七 一二五〇)
≪書き下し≫妹(いも)がため菅(すが)の実(み)摘(つ)みに行きし我(わ)れ山道(やまぢ)に惑(まど)ひこの日暮しつ
(訳)故郷で待ついとしい人のために山菅の実を摘みに出かけた私は、山道に迷いこんで、とうとうこの一日を山で過ごしてしまった。(同上)
(注)くらす【暮らす】他動詞:①日が暮れるまで時を過ごす。昼間を過ごす。②(年月・季節などを)過ごす。月日をおくる。生活する。(学研)
一二四九歌ならびに歌碑については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その1249)」で、一二五〇歌ならびに歌碑については、同「同(その1250)」で紹介している。
➡
■島根県益田市 県立万葉公園石見の広場万葉歌碑(巻四 四九七)■

●歌をみていこう。
◆古尓 有兼人毛 如吾歟 妹尓戀乍 宿不勝家牟
(柿本人麻呂 巻四 四九七)
≪書き下し≫いにしへにありけむ人も我(あ)がごとか妹(いも)に恋ひつつ寐寝(いね)かてずけむ
(訳)いにしえ、この世にいた人も、私のように妻恋しさに夜も眠れぬつらさを味わったことであろうか。(「万葉集 一」 伊藤 博 著 角川ソフィア文庫より)
(注)かてぬ 分類連語:…できない。…しにくい。 ※なりたち補助動詞「かつ」の未然形+打消の助動詞「ず」の連体形(学研)
四九六から四九九歌の歌群の題詞は、「柿本朝臣人麻呂歌四首」<柿本朝臣人麻呂(かきのもとのあそみひとまろ)が歌四首>である。
この歌ならびに歌碑については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その1265)」で紹介している。
➡
■島根県益田市 県立万葉公園石見の広場万葉歌碑(巻十一 二八〇二の『或本の歌』)■

●歌をみていこう。
◆足日木乃 山鳥之尾乃 四垂尾乃 長永夜乎 一鴨将宿
(柿本人麻呂? 巻十一 [二八一三] 二八〇二の或る本の歌)
※[二八一三]は、「新編 国歌大観」の新番号
≪書き下し≫あしひきの山鳥の尾のしだり尾の長々(ながなが)し夜(よ)をひとりかも寝む
(訳)山鳥の尾の垂れ下がった長い尾のように、何とも長たらしいこの夜なのに、独りわびしく寝ることになるのか。(「万葉集 三」 伊藤 博 著 角川ソフィア文庫より)
(注)しだりを【し垂り尾・垂り尾】名詞:長く垂れ下がっている尾。(学研)
(注)上三句は序。「長々し」を起こす。(伊藤脚注)
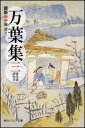 |
新版 万葉集 三 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) [ 伊藤 博 ] 価格:1,068円 |
![]()
この歌ならびに歌碑については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その1257)」で紹介している。
➡

万葉植物園ならびに周辺には、万葉歌碑(プレート)が多数立てられている。

(参考文献)
★「萬葉集」 鶴 久・森山 隆 編 (桜楓社)
★「weblio古語辞典 学研全訳古語辞典」」
★「コトバンク 講談社デジタル版 日本人名大辞典+Plus)」
★「しまね観光ナビHP」