●歌は、「磯の上に根延ふむろの木見し人をいづらと問はば語り告げむか」である。

●歌をみていこう。
◆磯上丹 根蔓室木 見之人乎 何在登問者 語将告可
(大伴旅人 巻三 四四八)
≪書き下し≫磯の上に根延(ねば)ふむろの木見し人をいづらと問はば語り告げむか
(訳)海辺の岩の上に根を張っているむろの木よ、行く時にお前を見た人、その人をどうしているかと尋ねたなら、語り聞かせてくれるであろうか。(伊藤 博 著 「万葉集 一」 角川ソフィア文庫より)
(注)いづら【何ら】代名詞:どこ。▽方向・場所についていう不定称の指示代名詞。(weblio古語辞典 学研全訳古語辞典)
 |
新版 万葉集 一 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) [ 伊藤 博 ] 価格:1,056円 |
![]()
四四六から四五〇歌の歌群の題詞は、「天平二年庚午冬十二月大宰帥大伴卿向京上道之時作歌五首」<天平二年庚午(かのえうま)の冬の十二月に、大宰帥(だざいのそち)大伴卿(おほとものまへつきみ)、京に向ひて道に上る時に作る歌五首>である。
四四六から四四八歌の三首の左注が、「右三首過鞆浦日作歌」<右の三首は、鞆の浦を過ぐる日に作る歌>で、四四九、四五〇歌のそれは「右二首過敏馬埼日作歌」<右の二首は、敏馬の崎を過ぐる日に作る歌>である。
題詞にあるように、天平二年(730年)大伴旅人が大納言に昇進し、大宰府から都に戻る途中、鞆の浦で詠んだものである。
大宰府は、「遠の朝廷(みかど)」と呼ばれ、主要職メンバーはすべて、遠隔の地からの赴任者であった。それだけに大宰帥の人選にあたっては内助の功を十二分に発揮できる妻をもっているかが条件とされたという。旅人の妻の郎女はそのような才能を有していたが、九州の着くと間もなく、長旅の疲れのせいか病床に就き帰らぬ人になってしまったのである。
赴任する時に、妻と一緒に見た「むろの木」が思い出されて、やるせない気持ちが溢れる歌である。
四四六から四五〇歌の歌群については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その895)」で紹介している。
➡
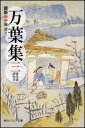 |
新版 万葉集 三 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) [ 伊藤 博 ] 価格:1,068円 |
![]()
万葉集巻十五には、天平八年(736年)六月に新羅に遣わされた使人たちの歌百四十五首からなる実録風的歌群が収録されている。
その中で、三五九四から三六〇一歌の歌群の左注は、「右八首乗船入海路上作歌」<右の八首は、船に乗りて海に入り、路の上(うへ)にして作る歌>とある。難波津から広島県鞆の浦までの航海上に詠った歌である。
三六〇〇、三六〇一歌は、鞆の浦の「むろの木」を見て詠った歌で、旅人の歌を踏まえている。
両歌をみてみよう。
◆波奈礼蘇尓 多弖流牟漏能木 宇多我多毛 比左之伎時乎 須疑尓家流香母
(遣新羅使人等 巻十五 三六〇〇)
≪書き下し≫離(はな)れ磯(そ)に立てるむろの木うたがたも久しき時を過ぎにけるかも
(訳)離れ島の磯に立っているむろの木、あの木はきっと途方もなく長い年月を、あの姿のままで過ごしてきたものなのだ。(伊藤 博 著 「万葉集 三」 角川ソフィア文庫より)
(注)うたがたも 副詞:①きっと。必ず。真実に。②〔下に打消や反語表現を伴って〕決して。少しも。よもや。 ※上代語。(学研)
◆之麻思久母 比等利安里宇流 毛能尓安礼也 之麻能牟漏能木 波奈礼弖安流良武
(遣新羅使人等 巻十五 三六〇一)
≪書き下し≫しましくもひとりありうるものにあれや島のむろの木離れてあるらむ
(訳)ほんのしばらくだって、人は独りでいられるものなのであろうか、そんなはずはないのに、どうしてあの島のむろの木は、あんなに離れて独りぼっちでおられるのであろうか。(同上)
(注)しましく【暫しく】副詞:少しの間。 ※上代語。(学研)
三五九四から三六〇一歌の歌群については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その623)」で紹介している。
➡


■■広島市安芸区上瀬野町上大山万葉歌碑→広島県福山市鞆町 医王寺■■
前回鞆の浦の万葉歌碑を巡った時、時間切れで医王寺はパスしたのであった。今回は、グーグルのストリートビューで確認をとっておいた。
駐車場に向かう上り道は勾配がきつくそのうえ車1台がやっとという幅である。
しかも、少し広めの道路から直角に路地に入るイメージで車を回さねばならない。悪戦苦闘である。
あまりの勾配のきつさに足腰の悪い家内は駐車場で待機することになり、小生単独行である。

境内についた時には、ゼイゼイハーハーである。歌碑巡りは体力勝負の世界である。
歌碑の近くから鞆の浦の絶景を見下ろしてほっと一息。歌碑と絶景、至福のひと時である。

福山市HP「ふくやま観光・魅力サイト」に医王寺について、「平安時代,弘法大師の開基と伝えられる真言宗の寺。後山の中腹に建つことから,眺望の良さでも有名です。境内からの眺めはもちろん,裏山の中腹にある『太子殿』からは,鞆の町と瀬戸内の景観を一望することができます。本尊である木造薬師如来像は,県の重要文化財に指定されています。」と書かれている。太子殿からの眺望はお預けである。
福山市内のホテルから福山城のプロジェクションマッピングが見られてこちらも満喫。



(参考文献)
★「萬葉集」 鶴 久・森山 隆 編 (桜楓社)
★「weblio古語辞典 学研全訳古語辞典」
★「ふくやま観光・魅力サイト」 (福山市HP)