■富山県高岡市太田 つまま公園万葉歌碑:安政五年(1858年)■
●歌は、「磯の上のつままを見れば根を延へて年深くあらし神さびにけり」である。

●歌碑は、高岡市太田 つまま公園にある。
●歌をみていこう。
◆礒上之 都萬麻乎見者 根乎延而 年深有之 神佐備尓家里
(大伴家持 巻十九 四一五九)
≪書き下し≫磯(いそ)の上(うへ)のつままを見れば根を延(は)へて年深くあらし神(かむ)さびにけり
(訳)海辺の岩の上に立つつままを見ると、根をがっちり張って、見るからに年を重ねている。何という神々しさであることか。(伊藤 博 著 「万葉集 四」 角川ソフィア文庫より)
(注)としふかし【年深し】( 形ク ):何年も経っている。年老いている。(weblio辞書 三省堂 大辞林 第三版)
(注)あらし 分類連語:あるらしい。あるにちがいない。 ※なりたち ラ変動詞「あり」の連体形+推量の助動詞「らし」からなる「あるらし」が変化した形。ラ変動詞「あり」が形容詞化した形とする説もある。(weblio古語辞典 学研全訳古語辞典)
 |
新版 万葉集 四 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) [ 伊藤 博 ] 価格:1,068円 |
![]()
題詞は、「過澁谿埼見巌上樹歌一首 樹名都萬麻」<澁谿(しぶたに)の埼(さき)を過ぎて、巌(いはほ)の上(うへ)の樹(き)を見る歌一首 樹の名はつまま>である。
この歌については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その867)」で紹介している。
➡
「つまま」が、万葉集で歌われているのは、この一首のみである。
「つまま」については、「植物で見る万葉の世界」(國學院大學「万葉の花の会」発行)に次のように書かれている。
「『つまま』についてはマツ・タブノキ・イヌツゲなど諸説あるものの、現在は海岸地に自生し、常緑で大木ともなるタブノキ(クスノキ科、一名イヌクス)がそれかとみられている。タブノキは越中・能登の地に多く、常緑高木は『神さびにけり』の感慨にもふさわしい。」
公園には、歌碑の説明案内板があるが、表面の経年劣化により読みづらくなっているが、写真を拡大して何とか読み取れたので記してみた。

「・・・この歌碑は、安政五年(一八五八)に太田村伊勢領の肝煎(きもいり)(村長)宗九郎(そうくろう)が建立したものとされ、高岡では、最も古い万葉歌碑である。宗九郎は、相当の学問があり万葉集にも関心が高く、特に、都萬麻(つまま)はタモノキであると推定して一本のタモノキとこの碑を置いたとされるが、永年の風食により碑の文字を判読するのは難しい。都萬麻は、クスノキ科の常緑高木で一般にもタモまたはタブノキと呼ぶイヌグスのこととされている。老木は根が盛り上がり神々しい姿である。このことから神聖な木として扱われることが多い・・・」
後半は、家持が越中国射水郡渋谷の崎で根を露出した見慣れない大樹に驚き、初めて聞く「都万麻」(つまま)の名に異郷の風土を感じ、この歌を詠い、眼前の光景が未来永劫に続くことを願って「都万麻」の歌を詠じたと書かれている。
江戸時代に万葉歌碑を建立する人がいたことに驚かされる。
このような時代を感じさせる歌碑に巡り合えるのも万葉歌碑巡りの魅力の一つである。
これまでに巡った歌碑の中で、江戸、明治に立てられたものをみてみよう。
■滋賀県東近江市下麻生 山部神社境内万葉歌碑:明治十二年(1879年)■

●歌をみていこう。
題詞は、「山部宿祢赤人歌四首」<山部宿禰赤人が歌四首>である。
◆春野尓 須美礼採尓等 來師吾曽 野乎奈都可之美 一夜宿二来
(山部赤人 巻八 一四二四)
≪書き下し≫春の野にすみれ摘(つ)みにと来(こ)しわれぞ 野をなつかしみ一夜寝(ね)にける
(訳)春の野に、すみれを摘もうとやってきた私は、その野の美しさに心引かれて、つい一夜を明かしてしまった。(伊藤 博 著 「万葉集 二」 角川ソフィア文庫より)
(注)なつかし【懐かし】形容詞:①心が引かれる。親しみが持てる。好ましい。なじみやすい。②思い出に心引かれる。昔が思い出されて慕わしい。(学研)
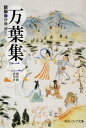 |
新版 万葉集 二 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) [ 伊藤 博 ] 価格:1,100円 |
![]()
この歌ならびに他の三首については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その417)」で紹介している。
➡
■兵庫県淡路市富島 JA淡路日の出北淡支店隣万葉歌碑:嘉永7年(1854年)かそれ以前■

●歌をみていこう。
◆珠藻苅 敏馬乎過 夏草之 野嶋之埼尓 舟近著奴
一本云 處女乎過而 夏草乃 野嶋我埼尓 伊保里為吾等者
(柿本人麻呂 巻三 二五〇)
≪書き下し≫玉藻(たまも)刈る敏馬(みぬめ)を過ぎて夏草の野島(のしま)の崎に船近づきぬ
一本には「処女(をとめ)を過ぎて夏草の野島が崎に廬(いほり)す我(わ)れは」といふ
(訳)海女(あま)たちが玉藻を刈る敏馬(みぬめ)、故郷の妻が見えないという名の敏馬を素通りして、はや船は夏草茂るわびしい野島の崎に近づきつつある。(伊藤 博 著 「万葉集 一」 角川ソフィア文庫より)
(注)たまもかる【玉藻刈る】分類枕詞:玉藻を刈り採っている所の意で、海岸の地名「敏馬(みぬめ)」「辛荷(からに)」「乎等女(をとめ)」などに、また、海や水に関係のある「沖」「井堤(ゐで)」などにかかる。(学研)
(注)敏馬(みぬめ):神戸港の東、岩屋町付近。「見ぬ女」の意を匂わす。(伊藤脚注)
(注)野島が崎:兵庫県の淡路島にある野島の岬。和歌の名所。(コトバンク 精選版 日本国語大辞典)
 |
新版 万葉集 一 現代語訳付き (角川ソフィア文庫) [ 伊藤 博 ] 価格:1,056円 |
![]()
この歌碑について、「飛鳥を愛する会 秋季現地講座 1:「飛鳥を愛する会 淡路・讃岐、吉備の史跡と万葉秀歌の舞台をめぐる旅」2016年10月2日~4日のブログ(日記)に詳しく書かれているので引用(一部加筆・省略)させていただきます。
「富嶋の文字の下には
玉藻加る 富し満遠過ぎて な川草の 野嶋可さ起尓 ふ年致何寿起奴
たまもかる とみしまをすぎて なつくさの のしまがさきに ふねちかづきぬ
万葉集巻3-250 柿本人麻呂 の歌が刻まれているとされていますが、現在は摩滅していて判読することはできません。
(人麻呂の歌は『敏馬』であるが『富嶋』となっている。詳細は下の丸型歌碑の説明にあります)
この歌碑は嘉永7年(1854年)頃かそれ以前に建立されたものと思われます。
根拠となっているのは、ここから4kmほど離れた『浅野公園』にある万葉歌碑の副碑の碑文です。『~中略 今地誌を案ずるに、ここを去ること一里ばかり机浦(つくえうら)、瀕海(ひんかい)の田中に碣(いしぶみ)を立つるあり。古歌一首 たまもかる 敏馬をすぎて 夏草の 野島が崎に 舟近づきぬ を勒(ろく)し、以てこれを表す。~中略』 (原文は漢文、勒し→刻むこと) (ここから4kmばかりの机浦(富嶋)の田の中に石碑がある。古歌 たまもかる 敏馬をすぎて 夏草の 野島が崎に 舟近づきぬ の一首が刻まれている。)
この浅野公園の副碑には嘉永7年(1854年)申寅3月の日付があります。すなわち、浅野公園の万葉歌碑の副碑が建立された時には、富嶋の歌碑はすでにあったことになります。」
浅野公園の万葉歌碑の副碑からこの歌碑が、嘉永7年(1854年)かそれ以前に立てられていたと推察されるのである。
この歌については、富嶋の歌碑の解説とともに拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その1947)」で紹介している。
➡
■兵庫県淡路市浅野南 浅野公園万葉歌碑:嘉永7年(1854年)■

●歌をみていこう。
題詞は、「羈旅歌一首 幷短歌」<羈旅(たび)の歌一首 幷せて短歌>である。
左注は、「右歌若宮年魚麻呂誦之 但未審作者」<右の歌は、若宮年魚麻呂(わかみやのあゆまろ)誦(よ)む。ただし、いまだ作者を審(つばひ)にせず>である。
(注)誦む:口誦した、の意。(伊藤脚注)
◆海若者 霊寸物香 淡路嶋 中尓立置而 白浪乎 伊与尓廻之 座待月 開乃門従者 暮去者 塩乎令満 明去者 塩乎令于 塩左為能 浪乎恐美 淡路嶋 礒隠居而 何時鴨 此夜乃将明跡 待従尓 寐乃不勝宿者 瀧上乃 淺野之▼ 開去歳 立動良之 率兒等 安倍而榜出牟 尓波母之頭氣師
▼は「矢+鳥=「きざし」
(作者未詳 巻三 三八八)
≪書き下し≫海若(わたつみ)は くしきものか 淡路島(あはぢしま) 中に立て置きて 白波を 伊予に廻(めぐ)らし 居待月(ゐまちつき) 明石の門(と)ゆは 夕(ゆふ)されば 潮(しほ)を満(み)たしめ 明(あ)けされば 潮(しほ)を干(ひ)しむ 潮騒(しほさゐ)の 波を畏(かしこ)み 淡路島 礒(いそ)隠(かく)り居て いつしかも この夜(よ)の明けむと さもらふに 寐(い)の寝(ね)かてねば 滝(たき)の上(うへ)の 浅野(あさの)の雉(きぎし) 明けぬとし 立ち騒(さわ)くらし いざ子ども あへて漕(こ)ぎ出(で)む 庭(には)も静けし
(訳)海の神は何と霊妙あらたかな存在(もの)であることか。淡路島(あわじしま)を大海(おおうみ)の真ん中に立てて置いて、白波をば伊予(いよ)の国までめぐらし、明石の海峡(せと)を通じて、夕方には潮を満ちさせ、明け方には潮を引かせる。その満ち引きの潮鳴りのとどろく波が恐ろしいので、淡路島の磯かげにひそんでいて、いつになったらこの夜が明けるかとじっと様子をうかがってまんじりともしないでいると、滝のそばの浅野の雉(きじ)が夜明けを告げて立ち騒いでいる。さあ、者どもよ、勇を鼓(こ)して漕ぎ出そうぞ。ちょうど海面もおだやかだ。(同上)
(注)くすし【奇し】形容詞:①神秘的だ。不思議だ。霊妙な力がある。②固苦しい。窮屈だ。不自然でそぐわない感じだ。 ⇒参考:「くすし」と「あやし」「けし」の違い 類義語「あやし」はふつうと違って理解しがたいもの、「けし」はいつもと違って好ましくないものにいうことが多いのに対して、「くすし」は神秘的なものにいう。(学研)
(注)ゐまちづき【居待ち月】名詞:陰暦十八日の夜の月。陰暦十七日の「立ち待ちの月」よりやや遅く十九日の「臥(ふ)し待ちの月」よりやや早く月の出があり、座って月の出を待つというところからこの名がある。季語としては、特に、八月十八日の夜の月をいう。居待ちの月。居待ち。[季語] 秋。(学研)
(注の注)ゐまちづき【居待ち月】分類枕詞:地名「明石(あかし)」にかかる。月を待って夜を明かすことからとも、十八日の夜の月が明るい意からともいう。(学研)ここでは枕詞として使われている。
(注)いつしかも【何時しかも】分類連語:〔下に願望の表現を伴って〕早く(…したい)。今すぐにも(…したい)。 ⇒なりたち:副詞「いつしか」+係助詞「も」(学研)
(注)さもらふ【候ふ・侍ふ】自動詞:①ようすを見ながら機会をうかがう。見守る。②貴人のそばに仕える。伺候する。 ※「さ」は接頭語。(学研)ここでは①の意。
(注)さもらふに 寐(い)の寝(ね)かてねば:様子を窺って寝るに寝られずにいると。(学研)
(注の注)いのねらえぬに【寝の寝らえぬに】分類連語:眠れないときに。寝ることができないでいると。 ⇒なりたち:名詞「い(寝)」+格助詞「の」+動詞「ぬ(寝)」の未然形+上代の可能の助動詞「らゆ」の未然形+打消の助動詞「ず」の連体形+接続助詞「に」(学研)
(注)庭:漁村の前に開けた海面。(伊藤脚注)
この歌については、拙稿ブログ「万葉歌碑を訪ねて(その1948)」で反歌三八九歌ならびにこの碑が立てられた経緯等について紹介している。
➡
■月読橋上流50mにある歌碑:文化二年(1805年)■

文化二年(1805年)に建てられた、新古今集の巻五、秋歌下に、題しらず柿本人麻呂の歌碑がある。
この歌の元歌は、万葉集の巻十 二二一〇歌(柿本人麻呂歌集)「明日香川もみじ葉流る葛城の山の木の葉は今し散るらむ」である。碑の裏に「文化2年歳次乙丑夏五月」と記されている。駒が谷の金剛輪寺の住職をしていた学僧の覚峰が文化二年(1805年)に建立したとある。
場所は、大阪府羽曳野市駒が谷、竹内街道と飛鳥川が交わるところの橋が月読橋であり、そこから50mほど上流にある。
この歌、歌碑等についてはブログ拙稿「万葉歌碑を訪ねて(月読橋番外)」のなかで紹介している。
➡
古い万葉歌碑を検索してみると行田市HP(行田市教育委員会)に次のように書かれている。
「浅間塚の上に鎮座している前玉(さきたま)神社の石段の登り口に高さ2mの一対の石燈籠が建っています。元禄10年(1697)10月15日、地元の埼玉村の氏子一同が奉献したもので、2基の竿に「万葉集」の「小埼沼」と「埼玉の津」の歌が美しい万葉仮名で陰刻されています。旧跡「小埼沼」の碑より56年前の建立で、万葉集に掲載された歌の歌碑としては、全国でも最も古いものの一つです。」
(注)「前玉(さきたま)」は「埼玉」の語源と言われている。
元禄十年(1697年)に灯篭に万葉歌を刻して奉納する学識等には頭が下がる思いである。

(参考文献)
★「萬葉集」 鶴 久・森山 隆 編 (桜楓社)
★「植物で見る万葉の世界」(國學院大學「万葉の花の会」発行)
★「weblio古語辞典 学研全訳古語辞典」
★「「飛鳥を愛する会HP」